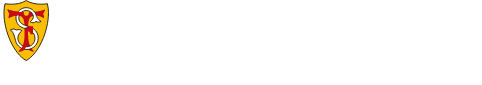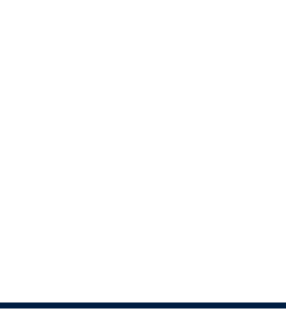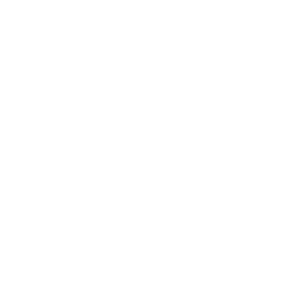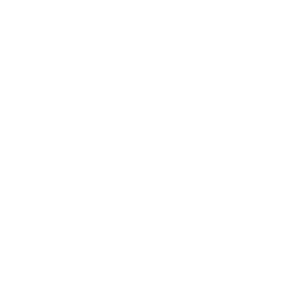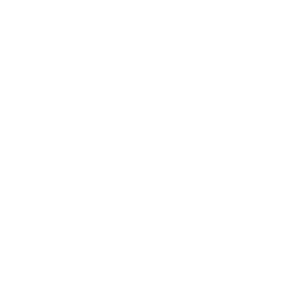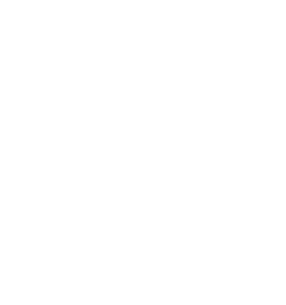【生徒作成記事】「好き」「楽しそう」「面白い」を仕事にする!(9/16UP)
2025.09.16
[授業]
S2選択科目「教養」では、生徒自身が興味関心を持つ分野について外部から講師をお招きし、学びを深めています。
7月3日にはマーダーミステリー作家であり、日本マーダーミステリー作家協会共同代表でもある、本校保護者の九尾まどか先生が来校。「“楽しそう”を仕事にする~マーダーミステリーという新しい文化の普及について~」というテーマでワークショップをしていただきました。
始めに、マーダーミステリー(以下、マダミス)の概要、他の遊びとの違い、マダミスの歴史について教えていただきました。マダミスはTRPGにごく近い、推理小説を体験するような遊びです。もともとイギリスの社交の場での余興としてパーティのゲストに提供されていたものですが、中国で人気を博し、約5年前に日本に入ってきた新しい遊びです。
お話を伺った後、4人ずつのテーブルに分かれ、実際にマダミスを体験しました。(制作・販売元、マダミス作家の方々のご好意で、無料で約40分のマダミスを体験しました。)とある一家でのハロウィーンパーティで起こった事件について、私たちはぞれぞれ役になりきり、自分の頭で考えて会話を進めました。ネタバレを防ぐため詳細は割愛しますが、最初の設定は同じでも、テーブルごとにストーリーが異なっていき、とても面白かったです。参加した生徒からは
「役に没入して、推理した」
「話の骨組み以外のストーリーがプレーヤーによって変わるというところがおもしろかった」
という感想が寄せられました。ぜひ皆さんもマダミスを体験してみてください。
マダミス体験後は、新しい文化を普及させることやそれを「職業」にすることについてお話してくださいました。
「好き」「楽しそう」「面白い」を続けるには経済の仕組みが必要です。様々なリソースを使って文化を生み出すので、文化の普及に関わる人々が「職業」として続けていけるように、収益化(マネタイズ)が必要になります。例えば、謎解き・脱出ゲームは収益化に成功しましたが、TRPGは二次創作にお金を払ってもらうという方法での収益化までに長い時間がかかったそうです。マダミスは、試行錯誤しながら、収益化に取り組んでいるそうです。
また、マダミスは作家だけではなく、デザイナー、店舗経営者、司会・スタッフ、アプリ開発者、イベンド会社の人など、様々な職業の人が関わっています。ひとつの新しい文化を発展させていくには様々な人との関わりが必要であることも知りました。
続いて、九尾先生はご自分のキャリアについて、学生時代にさかのぼって具体的にお話してくださいました。すぐにマダミス作家になったわけではなく、他の職業も経て、マダミス作家になったそうです。そして、そのすべての経験が生きているそうです。
自分がしていることを「職業」にするには、作品があり、収入があるだけでなく、さらに、日本〇〇協会のような公的認知が必要なので、日本マーダーミステリー作家協会を共同で立ち上げたこと。この3つに加えて、「社会的認知度」も必要だということもわかりました。
最後に、「好き」を職業にするには、自分をちゃんと「律すること」が大事とおっしゃっていました。仕事の締め切りを守ることが大切だからです。締め切りがあるお仕事をたくさん抱えて、毎日が宿題の提出前日の学生のようだそうで、「毎日が8月31日!」とおっしゃっていたのが印象的でした。
参加した生徒からは、
「職業として成立していないものを職業として確立させていくことの大変さを学んだ」
「やりたい!と思ったことが必ずしもマネタイズできるわけではなく、社会的に認知され、法的機関にも認知されないと難しいのだということが分かった。お話なさっているご様子が実に楽しそうだったので、クリエイター業に対して明るい、ポジティブな印象を持った」
「社会や経済のしくみを理解し、それを土台に仕事をすることが大事だと思った」
「少しでも好き!興味がある!と思ったら行動してみたい」
「自分をちゃんと律し、責任ある行動をとりたい」
「以前からマーダーミステリーには興味があったのだが、よく知らなかった。今回、設立・普及の始めの部分から知ることができてよかった」
といった感想が寄せられました。
このワークショップで体験したことを自分たちの将来に生かしていこうと思います。