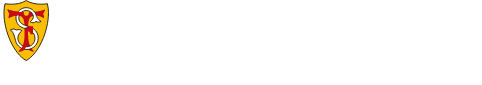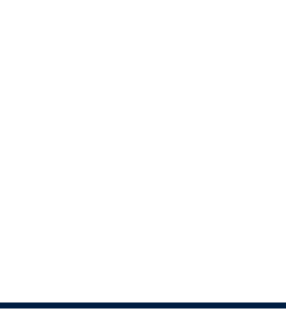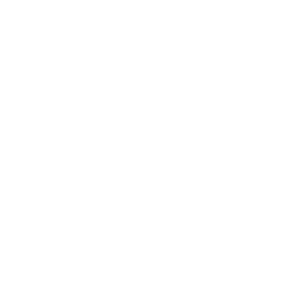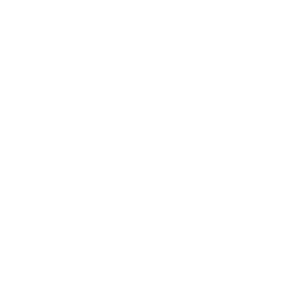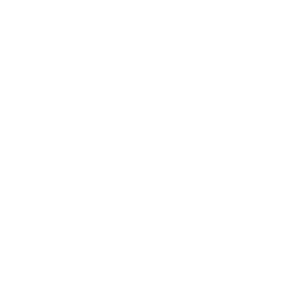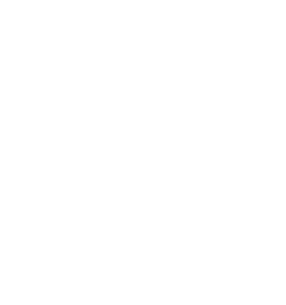「シリーズ:なぜ人は学ぶのか」②古典の先生にインタビュー(後編)(9/4UP)
2025.09.04
[プロジェクト]
>>>前編はこちら<<<
先週に引き続き、「シリーズ:人はなぜ学ぶのか②古典の先生にインタビュー」の後編をお届けします。
今回はいよいよ、B先生に「なぜ古典を学ぶのか」について語っていただきます!
Q1 古典は日常生活に役に立たないからやる意味がわからない、という生徒もいると思うのですが、先生にとって古典を学ぶ意義って何でしょうか。
これはよく訊かれます。古典を学ぶ意義というのは「外国語を学ぶ際の感覚の基礎とするため」や「グローバル化が進み多様な人々に囲まれる現代において、自分のルーツとなる国の文化や思想の歴史を基礎教養として学ぶため」などがよく挙げられますが、私自身はそれに加えてあと二つ、「自分と自分を取り巻く世界をより詳しく理解できるようになるため」「『見ぬ世の友』を探すため」というのもあるかと思っています。
一つ目は、古典というよりも国語という科目すべてに通底することだと思いますが、日常では目にしない言葉を知ることによって、これまで自分では認識できていなかった世界が見えてくる可能性があるということです。これはソシュールという言語学者の「言語が世界を分節する」という考え方に基づいています。彼いわく、私たちは目に見える景色や自分の感情を理解するとき、それに他とは違うなんらかの名前を付けることで、それがそれであると認識できるようになるとのことです。私たちに虹の色が七色に見えるのは、私たちが虹のグラデーションを七つに分割して、それぞれの範囲に赤とか黄色とか名前を付けているから、というのが分かりやすいでしょうか。逆に言えば、それに対する名前を知らないものについて、私たちはきちんとその存在を認識することができないわけです。
本題に戻ると、古典語には現代語では抜け落ちてしまった微細なニュアンスが含まれた言葉というのが多々あります。たとえば、主に「かわいい」と訳す「らうたし」は、ただかわいければ何にでも使えるわけではなくて、「守ってやりたい、世話を焼きたいと思わせるような存在に対する感情」を表す語ですし、「張り合いがない・物足りない・さみしい」などと訳す「さうざうし」は、「索索し」を語源とすると言われ、「あるべきものがそこにないので探しているような感覚」を表す語です。現代語でこれらを一語で直訳できる語はありませんが、私たちも人生の中で「らうたし」や「さうざうし」のような感覚を持つこと自体はありますよね。その時に、自分の中に生まれた感覚を「なんだかわからないもやもや」で終わらせてしまうのではなく、古語の中にある語彙で名づけることが出来れば、自分や他者、ひいては世界への理解がより深まると思うのです。これは生きてゆく中でとても大切なことではないでしょうか。
なぜなら、私たちは、「理解できない」ものに対して恐怖を覚えるからです。そうした恐怖は、時には自他に対する攻撃性を呼び起こしてしまうことすらあります。理解できないから、次に何が起きるかわからない。だから、自分が先に身構えておく、ということですね。でも、そうした自他に対する「わからなさ」の一端は、もしかしたらそれに対応する言葉を知らないことに起因するかもしれません。現代語・古典語・日本語・外国語問わず、多くの言葉を知ることで、少しでも名づけられるものが増えれば、無用な恐怖や対立が減るかもしれない。少し壮大ですが、私は古典もその一助になれると思っています。
二つ目は単純ですが、自分とぴったり寄り添ってくれる心の友となる作品を見つけられるきっかけになるということです。よく誤解されますが、ただ古い作品であるというだけでは「古典」にはなりません。ある作品が「古典」とされるためには、現代にも通底する価値観や感覚があり、また古代から現代まで連綿と引き継がれてきた日本的な感性が表れている作品であることが必要です。だからこそ、古典を読んだ時に、「え、私と同じこと考えている!」という発見があったり、「何百年も前に、私の悩みの解決策を書いている人がいたなんて……」と、時を超えた気づきが起こったりするのです。自分ひとりしか抱いていないように思われる悩みや理想、妄想(!)も、探してみれば案外古典の世界に先輩がいるものです。そして、古典は何百年も共感され、読み継がれて現代に残っているわけですから、現代に無数に存在する本の中から「友」となる一冊を探し出すよりも、私たちと似た感性を持った作品に出会いやすい分野だとも言えます。こうした時を超えて分かり合えるような本のことを、兼好法師は「見ぬ世の友」と呼びました。言い得て妙ですよね。
古典に即効性はありませんが、じわじわとみなさんの人生を照らし、闇の中にいるときには特に欠かすことのできない月の光のような学問だと思っています。
Q2 普段の授業では、どのようなことを心がけていますか。
主に二つあります。一つ目は、何事につけても根拠を持って教えること、二つ目は、なるべく様々な手段を使いながら、本質的な部分をイメージしやすい形で伝えることです。
一つ目に関しては、結論だけぽんと教えるのではなく、なぜそうなったのかという過程をしっかりと一緒に追ってゆけるような授業進行ができるようにしています。たとえば、現代語訳を取る際には、最初から文全体を大づかみに訳すのではなく、単語ひとつひとつを細かく判別して訳を取り、それらを漏れなくつなぎ合わせた逐語訳を取ることを徹底しています。ほんの一文字の訳であっても、それがわざわざ選ばれた理由があるということを実感してもらいたいからです。
わけのわからない古文が突然きれいな現代語訳になったら、ただ読む分にはいいかもしれませんが、自分で真似して訳してみろと言われた時には困りますよね。それに、たとえなんとなく雰囲気で真似して訳せたとしても、根拠がわからないままでは、いつまでも一か八かで訳し続ける羽目になってしまいます。そうではなく、なぜそうなったのかという根拠をひとつひとつ掴むことができれば、自分一人の時にも同じように訳せる力が付きます。それに、そのように細かい単語に注目することは、先述したような「ことば」への注意力を養うことにもつながると考えています。
二つ目は、ことばをことばで教えることの困難さに対して自分なりに工夫している点です。たとえば、「春過ぎぬ」の「ぬ」は動作の「完了」という意味を表す助動詞ですが、現代語に訳すと「春が過ぎた」「春が過ぎてしまう」などとなり、いまいちどういうニュアンスなのかがピンときませんよね。私はこういう時、英語の力を借りることがあります。” Spring has passed.” と「春過ぎぬ」の方が、現代語と古典語よりも感覚が近いと思うからです。現代日本語だと伝わりづらいニュアンスも、思い切って他の言語や絵・ジェスチャーなどの非言語表現の力を借りることで、案外直感的に理解してもらえることがよくあります。ですので、私はことばを重視してはいますが、あまりそれにこだわりすぎず、他の伝達手段がよさそうな時はどんどん取り入れるようにしています。
それから、あらたな単語を教えるときにも、そもそもどんな語義の単語なのか・どんなイメージが中心となっている語なのかをなるべく大げさに伝えるようにしています。イメージごと知ることで、その単語が生徒の中に新たな語彙として追加されると思っているからです。単に書いてある訳を覚えさせるのではなく、生徒たちの中でその語が語彙の一部となって生きていくように、なるべく感覚的にもすっと染み込むような伝え方を模索しています。(まだまだ修行中ですが…)
インタビューを終えて、古典とは、時を超えて、私たち自身や他者、そして言葉にならない感情を理解するための架け橋なのだと、改めて気づかされました。
きっとこれからも、多くの生徒が先生の授業を通じて、「見ぬ世の友」と出会い、自分の世界を広げていくことでしょう。
久しぶりに古典に触れたくなった読者の方へのおすすめは『徒然草』だそうです。一つの章が短く、読み易いことと、自分の人生に重ねて読むことができるとのことです。是非お手にとってみてください。
シリーズ:「人はなぜ学ぶのか」は、まだまだ続きます。次回のインタビューもお楽しみに!
<シリーズ:なぜ人は学ぶのか バックナンバー>
①世界史の先生 前編 ・ 後編
詩人・木下杢太郎の記念館にて

旅先で文学館があれば必ず立ち寄ります
蔦屋重三郎の展示にて

江戸時代の出版業に想いを馳せて…
同じく蔦屋重三郎展にて

大量の板本にわくわく!
夏休み明けの授業風景