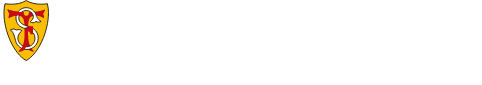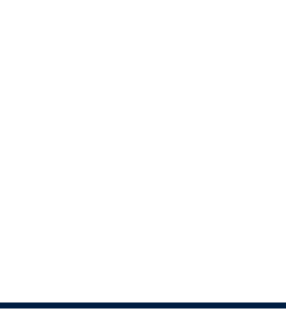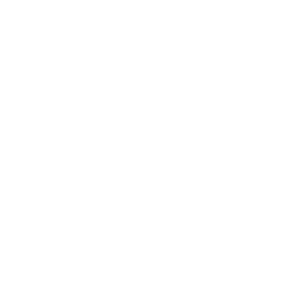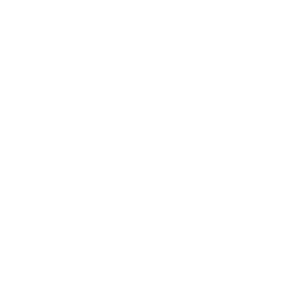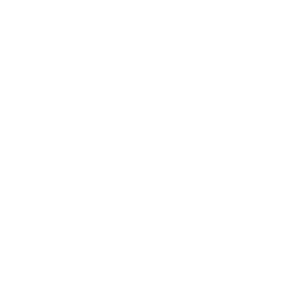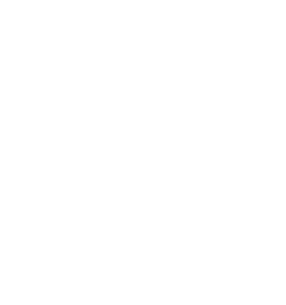「シリーズ:なぜ人は学ぶのか」②古典の先生にインタビュー(前編)(8/29UP)
2025.08.29
[プロジェクト]
「なぜ人は学ぶのか」という問いに正面から向き合う本企画。生徒からも「楽しみにしています!」という声を多くもらいました。
第二回目は、古典を担当しているB先生です。先生の授業は、豊かな教養と優しいお人柄が滲み出ていると評判です。一つ一つの訳を生徒が根拠をもって答えられるよう文法を論理的に解説し、また放課後も古典に苦手意識を持つ生徒を対象に特別講義を行うなど、熱心な指導で生徒の読解スキルを鍛えあげてくれます。
インタビュー前編は、普段はあまり聞けないプライベートの様子や、教員(2年目)としての想いを語って頂きました。
Q1 大学院ではどのような研究をされていたのでしょうか。
私は日本古典文学を専攻していて、特に専門は中世文学(およそ鎌倉時代~室町時代)でした。修士論文では兼好法師の『徒然草』と『兼好法師家集』という二つの作品を題材にしながら、兼好法師の「無常」と「美」の観念について研究しました。
特に注目していたのは「花は盛りに、月はくまなきをのみ、見るものかは(花は満開のときをだけ、月はかげりのない満月のときをだけ、見るものだろうか)」から始まる第一三七段です。
私は昔から、古びたものとか崩れかけたものに無性に惹かれる性質なのですが(アンティーク家具から古着、廃墟まで様々な古いものが好きです)、高校生の時にこの章段と出会って、古典の世界に自分とそっくりな考え方をこれほど明快に書き残していた人がいたことに衝撃を受けました。それと同時に、「兼好法師のものの見方をもっとよく知れば、それに照り返されるようにして自分自身のことももっとよく理解できるのではないか」と思ったんですね。そのことを大学生になって改めて思い出し、卒論から修論まで通しでこの作品を研究することに決めました。
Q2 卒業生でもあるB先生は、在学中から非常に成績優秀でしたが、普段の学習で心がけていたことは何ですか。
授業中にすべて完結させることです。これに尽きます。英語や古典なら全訳と単語まとめを授業中に完了させていましたし、他の科目も必ずその時間内に習うことはすべてその時間内にノートをまとめきっていました。部活もありましたし、家ではゆっくりしたかったので……。そんなわけで居眠りもゼロです!(大学院までの18年間、授業と名の付くもので居眠りをしたことがないのがひそかな自慢です)
Q3 教員としてどのような時にやりがいを感じますか。
やはり、「分からない」といって質問に来た生徒が、「ああ!」と納得して頷いてくれるときですかね。分からないことに対する不安やもやもやを解消する一助になれていると思うと大変やりがいを感じます。
それから、授業中でも授業外でも内容を深掘りして質問してもらえたときには、自分の行った授業を起点に生徒たちが自らの興味関心を広げていっている様子が垣間見られてとてもうれしく思いますね。フェリス生はとても鋭いので、質問の内容にその場で答えきれずに調べてから後日改めて回答することも多く本当に勉強になります。回答するために先行研究などを調べてゆくうちに、自身の大学院での研究と内容がつながってくることなどもあり、そういう時間はいつもとても楽しく、充実しています。
日々学び続けるチャンスを与えてくれる生徒たちには毎度感謝しています。
Q4 週末や長期休みといったプライベートの時間は何をしていますか。
フェリス時代の友人と遊びに行くことが多いですね。みな社会人になりましたが、卒業後も縁が切れることなく、定期的に会うことができていてうれしい限りです。映画を見に行ったり、カラオケをしたり、ショッピングをしたり、学生時代と変わらぬ気軽さで遊んでいます。誰と会っても笑いが絶えず、フェリス生と会う約束があった次の日はいつも表情筋が痛むほどです(笑)5月には、毎年恒例の薔薇を見る会(港の見える丘公園で薔薇を愛でる会合)に行き、とても楽しかったです。
一人の時は古着屋や本屋・美術館巡りをしたり、家で洋服を縫ったりしていることも多いです。お洋服と本が大好きなので、クローゼットと本棚がいつもはちきれそうです。
それから、大学時代の友人とお互い誘い合って文学館や古典関係の展示に行くこともよくありますね。最近は大河ドラマ「べらぼう」に関連する展示を見に行き、江戸時代の版本をたくさん見てきました。近世文学(主に江戸時代)が専門の友人と一緒に行ったので、さまざまな角度から知識を補完してもらえて、とても実りの多い一日でした。少しでも授業を豊かなものにしたいという気持ちで、もともとの専門ではない時代の展示にもなるべく顔を出せるように心がけています。
Q5 卒業生として、フェリスの魅力を一言で表すと・・
何事にも素直に全力を尽くし、納得するまで何かを追求し続ける芯があるところ!
前編は、常に知的好奇心にあふれ、日々の学びを存分に愉しむ感性と、教育者としてのプロ意識を兼ね備えるB先生の魅力が伝わるインタビューとなりました。生徒の皆さんも、先生の勉強方法を是非参考にしてみましょう。
さて、次回のインタビュー後編では、いよいよ「なぜ人は学ぶのか」という問いに向けて、研究者・教員の立場から古典を学ぶ意義を語りつくして頂きます。後編は来週更新予定です。お楽しみに!
卒業式の写真

高校時代の作家研究ノート

これが文学研究を志したきっかけだとか
正岡子規記念館にて