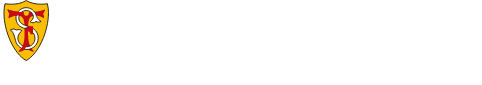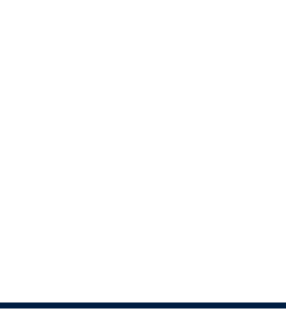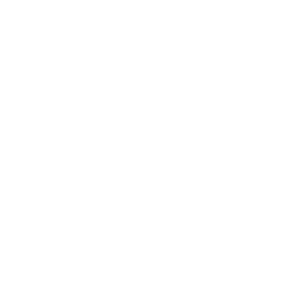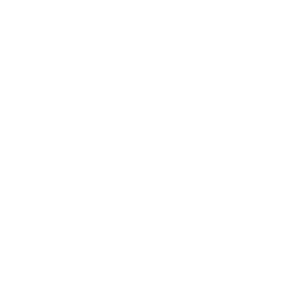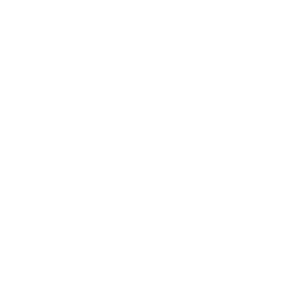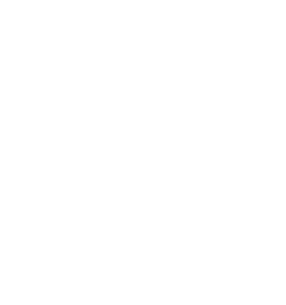【生徒作成記事】ゲーム理論入門(4/17UP)
2025.04.17
[プロジェクト]
3月、カリフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院教授の鎌田雄一郎先生と東京大学経済学部長の古澤泰治先生をお招きし、「社会問題を、数学で解決(?)〜ゲーム理論への招待〜」と題して模擬講義を行っていただきました。
最初に、古澤先生から経済学とは何かについてのお話がありました。経済学は、狭義には「人々が豊かに暮らせるように必要なものを必要なだけ届ける仕組み」と定義されますが、広義には「人や社会を考える学問」、つまり人・組織・制度を科学する学問とも定義されます。そのため経済学は、様々な規模の組織(部活から国連まで)の組織や運営に応用できるそうです。さらに最近ではデータサイエンスとしての経済学が注目されており、データから、相関関係だけではなく因果関係を読み取り、政策決定などに役立っているそうです。その一例として、「東大に行くとお金持ちになれるのか?」という例を使い、散布図を用いて分かりやすく説明して下さり、私たちの理解が深まりました。さらに、東京大学の経済学部で学ぶ内容や卒業後のキャリアなどにも言及してくださり、私たちが自分の進路を考える一助となりました。
その後、鎌田先生の講義に移りました。鎌田先生は高校時代、将来の夢が何度も変わり、東京大学農学部へ進学した後も経済学部の授業に興味をもち、その後ハーバード大学で経済学の博士課程に進み、現在のご職業に就いたそうです。鎌田先生は「興味がどんどん変わっていくことは良いこと。しかしいつも目の前の興味や進路への努力を精一杯していた。それがとても重要」とおっしゃり、とても心に残りました。
次に、先生が研究なさっているゲーム理論について、解説して頂きました。ゲーム理論とは複数人が意思決定をする時に、戦略的状況を数学的に記述し、分析することで、いわゆる読み合いの状況を分析するということです。実生活では、企業の価格競争・国家間の交渉・オークション・医師と病院のマッチングなどに応用されます。このゲーム理論について、先生は「囚人のジレンマ」「環境問題(羊飼いと羊と草原の利害関係の例)」「価格競争と利益(スマホの値段と売り上げの例)」「数量競争(魚の漁獲量)」の4つの例を、分かりやすい数学を用いて説明してくださいました。実生活で応用されるゲーム理論の仕組みや、意思決定を行うプロセスを理解して、その複雑さや論理の面白さを感じることができました。
最後に、先生から「とことん努力するかしないかが人生が上手くいくか行かないかの分かれ目」という力強いメッセージをいただき、そのためにはいつも頭の中で自分の目標について考えることが重要だというアドバイスをくださいました。
経済学から進路まで、盛りだくさんな内容を、聴く人を惹きつけるプレゼンと共に教えて頂いた、とても貴重な機会でした。ここで学んだ内容や感じたことを今後に生かしていきたいと思います。