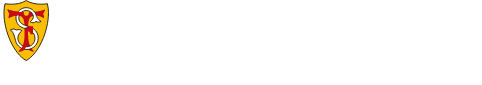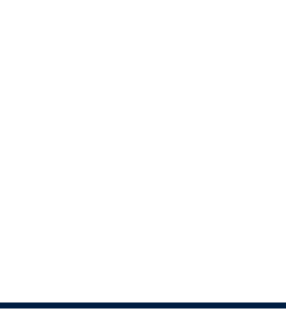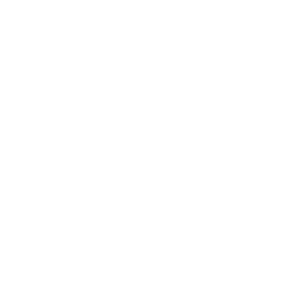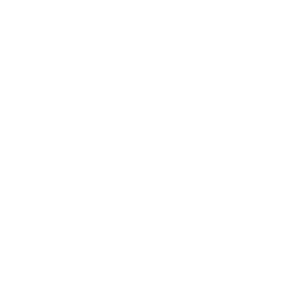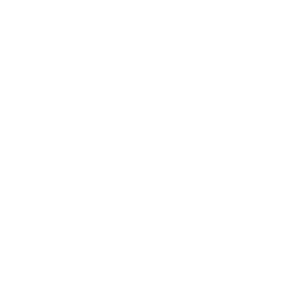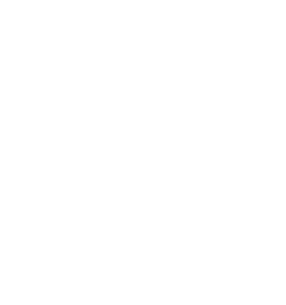広島で考える「核」と「平和」(4/11UP)
2025.04.11
[行事]
2月、S1(高1)の生徒たちが広島を訪れ、3日間の学びの時をもちました。
この広島研修旅行は1985年に始まり、以後40年にわたり続けられてきた本校の大切な行事です。
1980年代当時、被爆体験の風化が深刻な問題となる一方、欧州ではNATO軍によるヨーロッパへの核配備に伴う反核運動が高まっていました。こうしたなかで、当時の社会科教員たちは、生徒を実際に広島に連れて行き原爆の実態を学ばせたいと考え、現在に続くこの研修旅行を計画・実現しました。それから時が経ち、冷戦構造の消滅など、国際情勢は大きく変化しましたが、核の問題は解決されていません。核の実験場となった地域は広範囲の汚染に今もなお苦しみ、また近年では技術が向上したことにより、核の近代化・小型化が進んでいます。2022年には核保有国であるロシアがウクライナに侵攻し、核の脅しを繰り返すなど、国際安全保障がより一層不安定になっています。そのような時代だからこそ、核兵器の存在と世界の平和について考えるこの研修は、とりわけ重要な意義を持つものになっています。
研修初日、西日本に最強寒波襲来という情報にハラハラしながら広島に降り立ち、まずは平和記念資料館を見学しました。その後はグループに分かれ、広島女学院の生徒さんと一緒に平和公園およびその周辺を歩きながら、様々な慰霊碑について解説していただきました。両校の交流会ではそれぞれの代表が発表をしたのち、各グループで意見交換を行いました。同世代の生徒同士の交流は、初対面にも関わらずどんどんと仲が深まり、時間があっという間に過ぎてしまいました。
研修二日目は、いくつかのコースに分かれてフィールドワークに出かけます。広島市内の原爆の実相を伝える跡地を巡るコース、かつて「帝国海軍」の重要拠点となった呉市を訪れ日本の加害の側面を考えるコース、山間部を訪れ「黒い雨」が降った現場を歩き、黒い雨訴訟について考えるコースなど、実際に自分の目で見、耳で聴き、足で歩くことでしか得られない貴重な経験をすることができました。
宿に帰ってからのディスカッションでは、それぞれ自分が感じたことを友人とシェアし、本来30分程度の予定が、一時間以上も話が止まないグループもあり、教員も「まだ話していたの!?」と驚くほどでした。
生徒たちにとっては、コースの中で被爆証言を聴いたことが特に心揺さぶられる体験だったようです。90歳を超えてもなお、自分たちのために声を振り絞って当時のことを語ってくださる被爆者の方のお話を聞いて、涙が止まらなかった生徒もいました。
三日目は、世界各地の核被害を取材してこられたジャーナリストの方や、核のない世界を目指して行動を起こすアクティビストの方の講演を拝聴し、平和へのアプローチについて新たな視点を得ることできました。
楽しむための観光旅行ではない、「じっくり学ぶ」3日間のプログラム。S1は、教科の垣根を越えて「核」と「戦争」について、様々な視点から事前学習を重ね、本研修に臨みます。そして書物や机上からは得られない生の体験を通して、単なる“過去”としてではなく、当時の現実の中にあった被爆の実相を想像し、“いま”に繋げていきます。
ある生徒は今回の研修をふり返り、「これほどまでに強く心が動いた事が自分でも信じられなかった。確実に自分の人生の何かが変わった。」という感想を寄せてくれました。一人ひとりが「地球市民」として、国境や人種を越え、世界をより平和的、包括的で安全な持続可能な社会にしていくために、自分たちに何ができるだろうかと問い続けていく。その入り口の一つが広島研修旅行であると言えるでしょう。
広島女学院の生徒さんに案内して頂きました

平和記念資料館の見学

広島市内の原爆跡地を歩きます

講義で学びを深めてゆきます