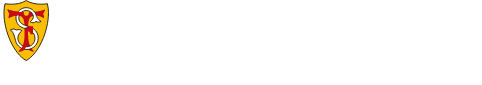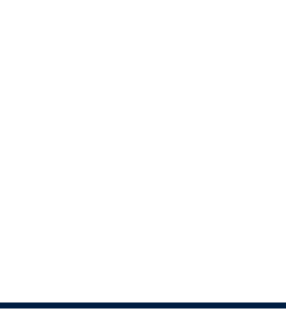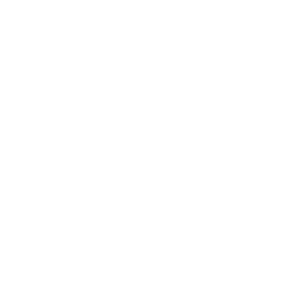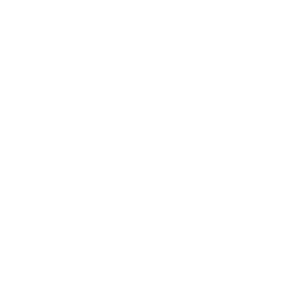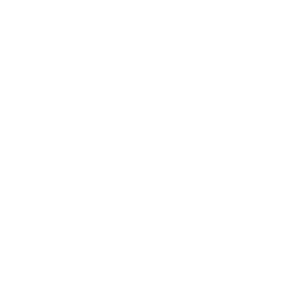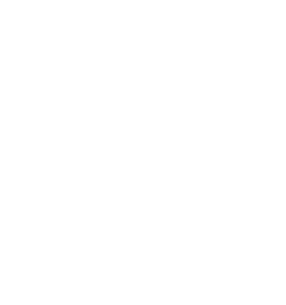授業探訪:「歴史総合」~100年前の哲学者からの問いかけ~(7/25UP)
2025.07.25
[授業]
2022年度から高校歴史分野の必修科目として新設された「歴史総合」をご存じでしょうか。今年(2025年)は、初めて共通テストでも出題され、どのような問題が出るのかと注目を集めました。
これまで高校では「日本史」「世界史」と分けて学習してきましたが、その2つを融合し、従来のような通史型ではなくテーマ史型(三大テーマ:近代化、大衆化、グローバル化)の構成をとることが、この科目の特徴です。
そして、学習の際に重要となるのが、歴史史料・写真・グラフといった多様な資料から根拠を得ながら、生徒自身が気づき、理解を深めるという姿勢です。
今回はS1(高1)歴史総合の授業にお邪魔し、「大衆とは何か?」という問いを考えるグループワークを取材しました。(※取材は2024年度に行いました。)
20世紀前半の世界は、歴史の表舞台に初めて「大衆=mass」が登場するようになります。国民の大多数が政治的参加を果たし、経済力もつけ、大衆の意見が国家の方針に大きく影響を及ぼす「大衆社会」の到来です。
今日の授業で扱う史料は、スペインの哲学者オルテガ・イ・ガセット(1883 -1955)による名著『大衆の反逆』です。オルテガは本書で大衆の持つ危険性を鋭く論じ、今からおよそ95年も前の著作であるにも関わらず、現在、そして未来をも見通すような言葉が散りばめられていて驚かされます。
高校生にとっては非常に難解な文章ですが、グループでじっくりと読み進め、オルテガの指摘を元に、現代の民主主義の問題点や限界についてディスカッションし、自身の言葉で「大衆とは何か?」という問いに対する答えを論述としてまとめていきます。
最初は「単語はわかるけど、文章として頭に入ってこない。」「結局何が言いたいの?」と弱音も聞こえてきますが、グループで話し合ううちに、「生徒会の選挙を例として考えると・・」「以前授業で学んだ、排外主義に繋がってしまうっていうことなのかな」と徐々に自分の持つ知識や経験と結び付けて、建設的な議論が生まれます。
私たちは「わからない」状況が苦手です。すぐにスマートフォンで答えを検索し、それらしきものを見つけて安心して、それを学びとしてしまうことがあります。しかし、本当に養うべきは「わからない」に向き合い、考え続ける力です。時間が許す限り議論を続け、思考することを楽しむフェリス生たちの活気があふれる授業の一コマでした。
最後に、一年間の歴史総合の授業を受けた生徒たちの感想をご紹介します。
・「ディスカッションやwork(注:workとは、史料や図表の読み解き問題などの総称)で自分の頭を使って考えたことで、ただ受け身で知識を詰め込むだけではなく、主体的に学ぶことが出来た。論理的に考え、自分の考えを文章化する力が身に付いたと思う。」
・「ただ座って授業を受けるだけではなかったので、飽きずに授業を受けることができた。加えて、workで引用された資料の中に興味深い本もたくさん見つけることができ、読書の幅が広がった。」
・「今年一年で『歴史を学ぶ』ことはただ史実を覚えることではなくて、過去のことをときに納得したり、ときに批判的に見たりして、現在につながる問題としてとらえることなのだと分かった。一年をとおして、とても楽しかった。」
グループディスカッションの様子