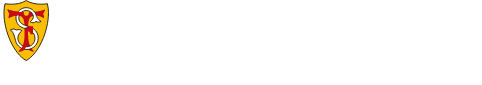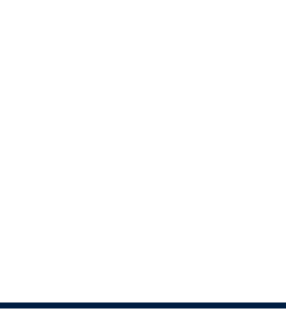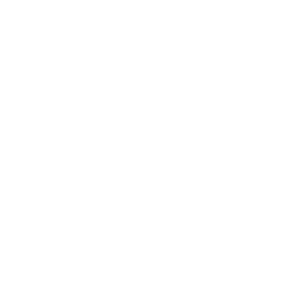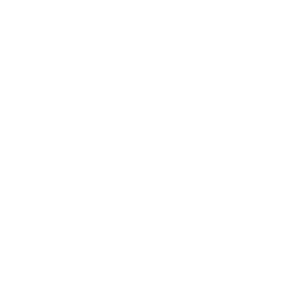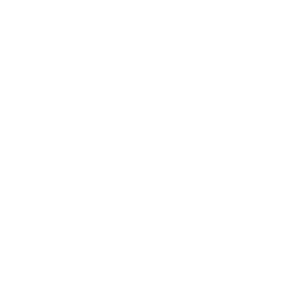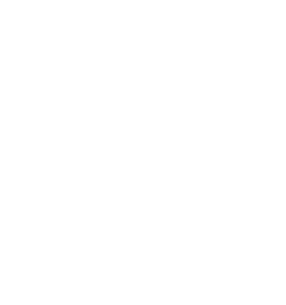授業探訪:「幾何」~図形に塩をふりかける~(3/7UP)
2025.03.07
[授業]
中学の幾何は、図形の性質を深く理解し、計算や証明を通じて論理的な思考を養うことを目指しています。こうした思考力を身につけることで、地図上での距離の計算、建物の面積や体積の計算、デザインや建築など、実生活の問題に応用することもできます。
今回はJ2「幾何」の授業にお邪魔し、塩を用いた実験の様子を取材しました。
生徒たちは事前学習として、五心(重心・内心・外心・垂心・傍心)を学び、本実験に取り組みます。バットと計量カップ、さらさらのお塩を用意して、いろいろな図形の台紙の上から塩をかけていきます。どのような形が現れるか、まずはグループで予想します。グループで考えがまとまったら、実験スタートです。計量カップから優しく塩をかけていきます。円錐になったり、三角錐になったり、家の屋根みたいになったり、様々な形状が現れます。クラスのあちらこちらから「おぉ~」と歓声が上がります。想像通りになったグループも、意外な結果になったグループも、どうしてそのような形になったのか、今度はその理由を考えます。塩は各辺からバットに落ちていくので、辺からの距離が等しくなる内角の二等分線が稜線となりあらわれます。
そして最後に穴の開いている図形に塩をかけていきます。円の中に穴(穴の位置は真ん中ではない)が開いている図形を使うと、何があらわれるのか・・?答えはヒミツです!
いつもは紙に書いている図形や計算式を違う角度から見ると新しい発見があり、理解が深まります。どうしてそのようになるのかを様々な角度から考察し、仲間と話し合うことで、これから未知の問題に出会ったときにもどのように考えたらよいのかというヒントになります。内心の性質も体感として忘れないものになっていることを期待します。
皆で楽しく塩をかけます

三角形の台紙に塩をかけると・・

穴の開いている図形はどうなるか・・