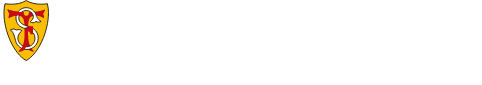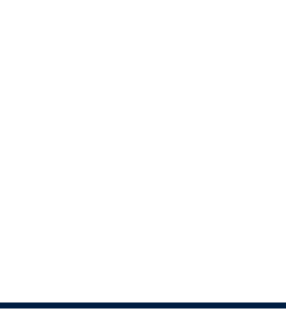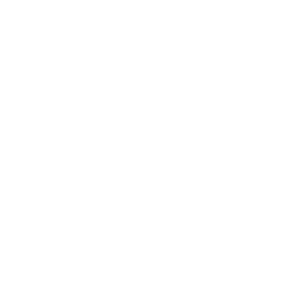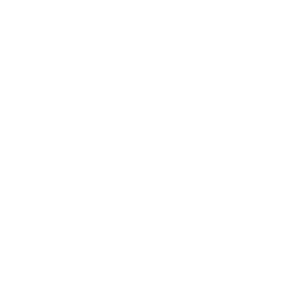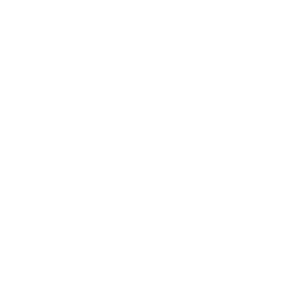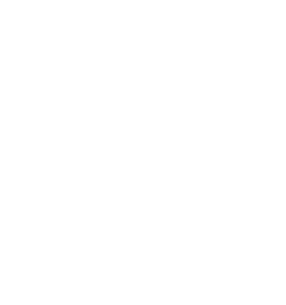自分ごととして「平和」を考える―高校生平和大使活動報告会(12/6UP)
2024.12.06
[行事]
本校は、スクールポリシーの一つとして「平和を希求し、一歩一歩その実現への道筋を拓く」を掲げています。その実現のために、S1(高校一年生)での広島研修旅行をはじめとする各種プログラムやその事前学習のための授業などを通じて、生徒たち一人一人が平和について自ら考え、行動する力を日々養っています。
さて先日、有志の生徒向けに、神奈川県の高校生平和大使として活動している本校生徒による活動報告会がありました。高校生平和大使とは「核兵器の廃絶と平和な世界の実現」を目指す高校生の団体で、国連に届けるための高校生一万人署名活動や平和活動のための研修・発信活動等を主に行っています。今年度、神奈川県では大使一名と署名サポートメンバー4名の計5名で県内を中心に活動を行ってきたそうですが、8月には全国の大使と共にスイス派遣に参加し、国連軍縮部への署名の提出ならびに軍縮や平和活動に関わる国連の組織へのスピーチ・意見交換等を行ったとのことです。
この高校生一万人署名活動は先週本校でも行われ、2日間で388筆もの署名が集まりました。大使はこのことについて、「普段街頭などで署名活動をしていると、『現実を見ろ』や『高校生がこんなことをやっても無駄だ』などの批判的な声にさらされることも少なくないが、フェリスでは賛同する人々に多く恵まれた。この活動を肯定し、署名にも快く協力してくださった皆さんに心から感謝している」と言っていました。実際、署名活動の手伝いを申し出た生徒も15名いたとのことで、生徒たちの中の平和活動に対する関心の強さがうかがえるエピソードです。
大使からの報告は活動紹介のほか、スイス派遣での経験やそこからの学び、また核を巡る世界の現状とそれに対する彼女の考えについてなど多岐にわたりました。核を巡る現状については集まった生徒たちに対して問いを投げかける瞬間もあり、生徒たちは周囲の友人ともよく話し合って真剣に話に耳を傾けている様子でした。
中でも印象的だったのは、歴史を自分ごととして捉えなおす必要性について説いていた場面です。大使はS1の広島研修旅行の際に被爆者の方の高齢化を実感し、近い未来に到来する「被爆者なき時代」の深刻さに気付いたことをきっかけに、この活動に関心を持ったそうです。彼女は活動報告会にて、カラー復元された原爆投下直前の長崎で暮らす人々の写真を見せながら、「被爆者となった人々も、直前まで現在の自分たちとなんら変わらない生活があり、大切な人がいて、夢があった。客観的事実としての歴史だけを学んでいると、そうした実際の人々の姿や生活は見えてこないので、私たちはついつい歴史に対して無関心に陥ってしまう。そうした『心の麻痺』に気づき、日本で学ぶ高校生として、日本で暮らす者として、それ以前に一人の人間として、過去の歴史を自分の頭だけでなく心で理解し、『自分ごと』として捉えなおすことが、未来の平和構築において必要なことだ」と述べていました。今回集まった生徒の中には、今年度広島研修旅行へ向かうS1も多く、この箇所で特に大きく頷いて先輩の言葉を真摯に受け止めている様子が見えました。研修旅行の事前学習も徐々に始まってくる時期ですので、大使の言葉はS1の生徒たちの学びへの姿勢にも影響を与えることでしょう。
また、もう一つ印象的だったのは、スイス派遣を通じて「対話」の重要性を学んだというお話です。現在、核を巡っては、「核廃絶論」と「核抑止論」など、異なる立場からの多様な意見が存在しています。このような意見対立は一朝一夕に解決するものではありませんが、「対話」(「同意はできないが理解はできる」、「相手の背景を理解する」)を実行してゆくことが解決への第一歩であることは紛れもない事実です。ただし、大使はスイス派遣でディスカッション等を経験する中で、自分と意見の違う相手とどのように意見をすり合わせるか、という問題は軍縮の専門家でも言葉に詰まるほど難しいということも同時に目の当たりにしたそうです。
フェリスは全校として「対話」を重視しており、授業内外のあらゆる問題に関して、相手を問わず活発に意見交換ができる雰囲気が保たれています。「対話」とは相手を自分側に折れさせるのではなく、相互の状況を整理し理解したうえでよりよい選択を行えるよう協議することですが、これは並大抵の努力では達成できません。今回の話から、日々こうした練習を積み重ねてゆくこと、そうした雰囲気を継承することの重要性を教員としても改めて実感しました。
報告会の最後には、参加した他の生徒に対して「高校生には一夜にして世界を劇的に変える力はないが、今しか持てない情熱や言葉の力がある」との助言もありました。たとえ今は草の根活動であっても、継続することで人々の意識を少しずつ変えることはできるし、人々の意識が変われば、世界も変えることができる。この考え方は、平和の実現への道筋を「一歩一歩」歩むことを目指すフェリス生にとって本当に重要なものです。
報告会終了後には集まった生徒たちから大使へいくつか質問も飛び、友人同士で報告会について語らう生徒の姿もちらほら見えるなど、みな彼女のお話に非常に刺激を受けた様子でした。今回の報告会には、J1(中学一年生)からS2(高校二年生)まで多様な生徒が集まっていました。その各々が今回の学びを自分の置かれた環境へ持ち帰ることで、「平和を希求し、一歩一歩その実現への道筋を拓く」姿勢が今後本校全体へさらに広がってゆくことを祈っています。
この記事に掲載された写真の二次利用は固く禁止します。ご注意ください。
報告会に耳を傾ける生徒たち

大使たち

スイス派遣の様子