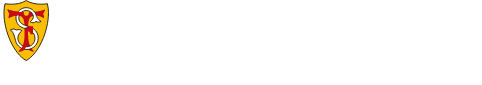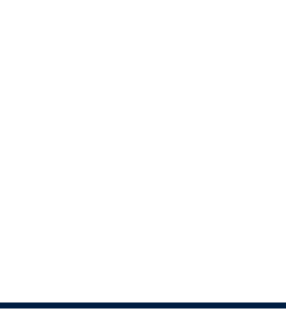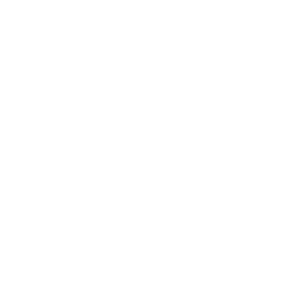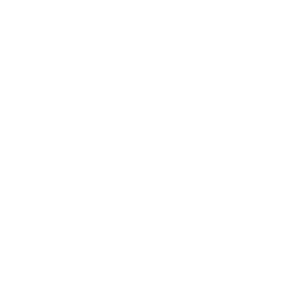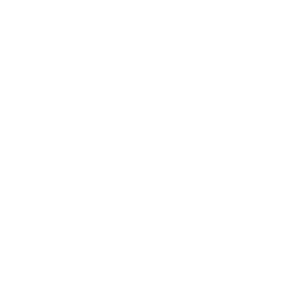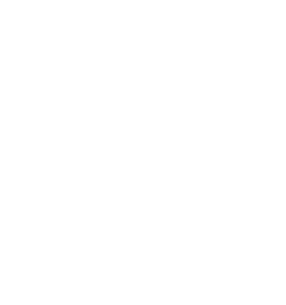【生徒作成記事】木下先生と学ぼうの会~芸術家に学ぶ、アート鑑賞~(11/28 UP)
2024.11.28
[授業]
S2選択科目「実践教養」では、現代アートとはどういうものなのかを探るために、フェリスの美術講師で、芸術家でもある木下拓也先生をお招きし、先生が作成した作品を用いて「木下先生と学ぼうの会」という鑑賞会を行いました。この会では希望した生徒4人が中心となり、生徒のみで会の設置や段取りを行いました。椅子や机の配置を行った後に、皆で二人一組になって並び、アーチ状に手を合わせて先生を出迎えました。また、会の始まりと終わりにwelcomeスピーチ、thank youスピーチを行い、感謝の気持ちを表しました。
この会を行うにあたって、生徒は事前学習として先生の作品を鑑賞、考察し、担当した作品のタイトルを自分で決め、作品の魅力はどこにあるのかについて味わいました。この際、「対話型鑑賞法」と呼ばれる芸術鑑賞の方法を用いました。「対話型鑑賞法」とは、自分の感情やなぜそう感じているかに意識を向けながら、観ること、思考すること、他の人の意見を聞くこと、自分の意見を伝えることの4つの動作を繰り返して考察を深める方法です。この「観ること」では、五感を総動員して、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の観点から作品を観察しました。「思考すること」では、観察したことだけでなく自分の持っている知識も活用して、鑑賞する視点を増やしていきました。他の人の意見を聞くことで、更に視点を増やし、自分の意見を伝えることで、考えた事を順序立てて整理しました。
当日はまず、事前に用意した考察を一人ずつ先生の前で発表しました。その後に、先生がその作品を作った意図や、どのような画材、画法で書いたのかなど自由に質問をして、答えていただきました。私たちは事前学習では、作品にストーリー性やメッセージ性を見出し、絵には必ず細かい所にまで必ず意図があるのだと思い込んでいました。そして、自分の立てた作品に対しての考察を否定されることを恐れていました。しかし、木下先生はどんな考察でも真剣に話を聞き、「そういう見方もあるのか」と受け入れて下さいました。また、「アートは自由なものであるため、自分ではコンセプトをはっきりと決めすぎず、受け手に委ねることが多い」とおっしゃったのを聞き、自分の好きなようにアートを楽しめば良い、ということに気づく事が出来ました。そして、自由な発想で作品に向き合うことが大事だということを学びました。
最後に先生から、会全体を通しての感想を頂きました。先生は、「制作においては、同じ作品に長い期間をかけて向き合うため、自分では気が付かなかった深層心理が作品に出てしまうのかもしれない。そして、鑑賞された事によってそれが表面化した。そうすることによって作品がより面白いものになった。」と言って下さいました。その言葉を受け、アートとは相互的なものだということを再確認することができました。
私たちは、この会を通してアートの面白さ、自由さを知りました。現代アートとは、もっと堅苦しくて難しいものに感じていましたが、自分の直感を信じて好きなように掘り下げて行けば良いと学ぶことが出来ました。これからは、もっと意欲的に知識を取り入れ、様々な作品に触れて、色々な視点に立ち、しかし肩の力を抜いてアートに親しんでいきたいと思います。
※本記事は記事作成の他、写真撮影および写真の選定も生徒が行いました。