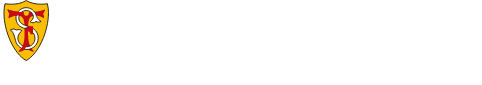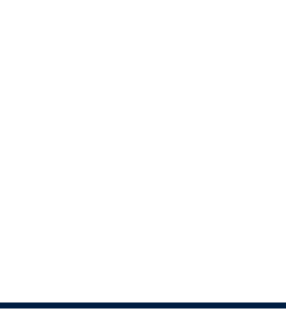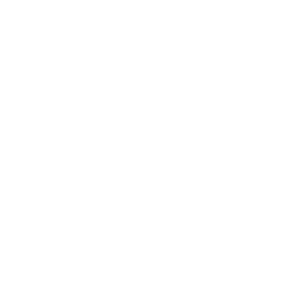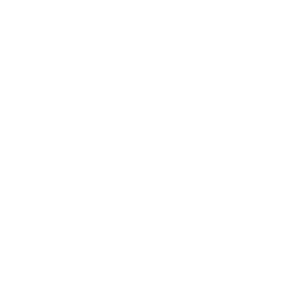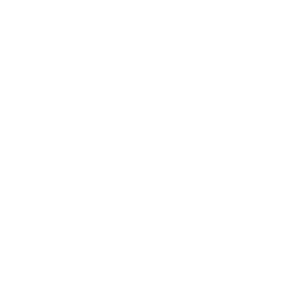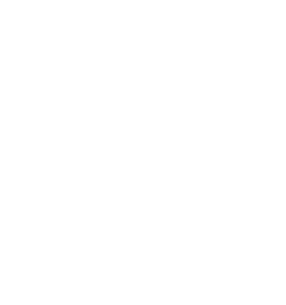新型コロナウイルス学者の先生に聞いてみよう―S1出張講義(9/3UP)
2024.09.03
[授業]
7月11日、本校では東京大学医科学研究所の佐藤佳教授(システムウイルス学)をお招きし、S1(高校一年生)向けに出張講義を行っていただきました。
佐藤先生は、2021年1月に若手研究者で構成された研究コンソーシアム(共同事業体)・G2P -Japanを結成され、長きにわたるコロナ禍の中で、変異株研究をはじめとした新型コロナウイルス研究の最前線を牽引されてきた研究者でいらっしゃいます。今回は生徒たちから事前に集めた質問をベースに、Q&A方式で専門知識や先生のご経験に基づく貴重なお話を伺うことができました。
Q&Aは大まかに「進路について」「研究という仕事について」「専門領域(ウイルス学)について」の三分野に分けて進行していただきました。
まず「進路について」では、佐藤先生ご自身が高校生の時に進路選択をされた時のお話を伺いました。先生は当時、バイオテクノロジーの最先端領域を学べるという理由から、他学部と比較した上で農学部への進学を決断されたそうです。ですが、今回はその後のご自身の研究上の経験をもとに、「ある学問をするにあたって、入り口となる学部はどこでも問題がない。なぜならば、学問とは本来、学際的に分野を横断して広がってゆくものであるから。ある領域を学ぶにあたって、学部という分け方は本質的には意味をなさない」とのご助言をくださいました。この考え方は進路について考え始めたS1にとって非常に印象的であったようで、多くの生徒がうんうんと大きく頷きながら懸命にメモを取っていました。
また、「研究という仕事について」では、先生が研究職を志したきっかけや研究職のやりがいと困難、日本における若手研究者の現況などに関する質問にお答えいただきました。中でも、「研究職という仕事の魅力は、“研究対象も方法も自分で決められるという自由さ”にある」や「楽しく研究していることが人の役に立つから研究を続けている」といったお話は、生徒たちが抱いていた「研究職」に対するイメージを良い意味で大きく変えてくださったようでした。
最後に、「専門領域について」では、新型コロナウイルスや鳥インフルエンザ等の身近なウイルスのお話を中心に、ウイルス研究のよもやま話を伺いました。先生はお話の最後で、「ウイルスの恐ろしさとは、常に想定外のことを起こすところ」であるとおっしゃいましたが、S1は入学してから数年の間、コロナ禍で制限の多い学校生活を送った学年で、ウイルスが引き起こす予想外の事象を身をもって経験しています。そのため、いっそう実感のこもった真剣な面持ちで先生のお話に耳を傾けていました。
そして、これら全てのお話が終わった後には、講義の内容について友人と話し合いながら教室を後にする生徒や、先生を囲んで追加の質問をする生徒も見受けられ、生徒たちがこの度の講義から大いに刺激を受けたことがうかがえました。
さて、今回の出張講義開催の直接的なきっかけは、佐藤先生のご著書『G2P-Japanの挑戦 コロナ禍を疾走した研究者たち』の出版と同書の高等学校への寄贈でした。先生はコロナ禍の日本で、“研究が行える若手研究者の不在”という大きな課題を見出し、それへの対処の一形態としてG2P-Japanという組織を結成されましたが、こうした若手研究者を巡る現況は、今後も長く向き合い続ける必要がある課題です。そして、今後新たに自らの進路を決めてゆく高校生たちは、この課題を改善するための重要な鍵となることでしょう。
一般的に、理系で、さらに研究職となると、どうしてもイメージだけで敬遠してしまう生徒が多いものです。しかしながら、今回の講義はそうしたイメージを打ち破り、生徒たちがこれまで無意識に視界から避けていた進路の選択肢を解放してくださるような内容でした。
この講義を受けた生徒たちが、イメージや固定観念にとらわれず、また自らの能力にむやみにブレーキをかけることもせずに、広い視野でもって自らの歩む道を決められるようになることを、教員の立場としても強く願っております。
★今回の出張講義の模様はG2P-Japan ConsortiumのXにも投稿していただきました!
ぜひ下のリンクよりご覧ください。
G2P-Japan Consortium X
学問の領域についてのご説明

DNAの二重らせん構造を発見したワトソン博士と佐藤先生のお写真!

講義終了後質問に集う生徒たち