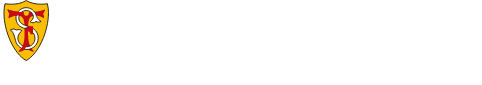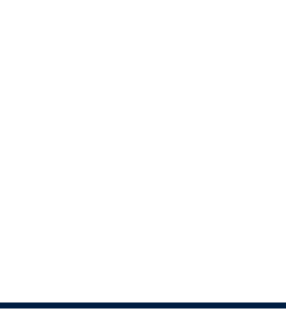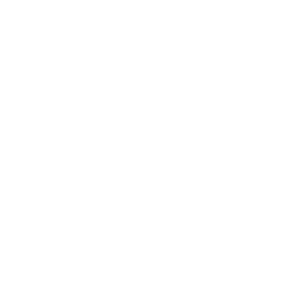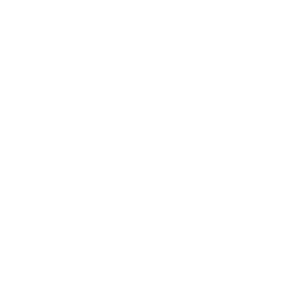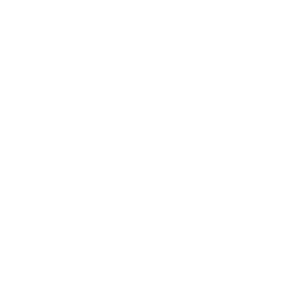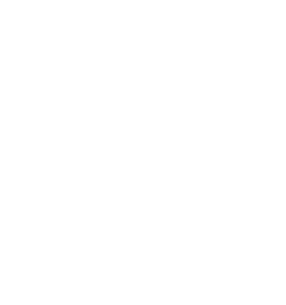「ことば」を使って議論する―S2「国語表現」(6/21UP)
2024.06.21
[授業]
フェリス女学院高等学校には様々な選択科目が置かれており、生徒たちはそれぞれ自らの興味に応じてこれらを選択・履修することができます。この選択科目の中には、必修科目とはひと味違った多様な学びの実践の場として機能している授業が数多く存在します。
今回は国語科選択科目の一つであるS2(高校二年生)の「国語表現」を取り上げ、授業内で行われたディベートの様子についてご紹介します。
本日取り上げる授業では、「フェリスに給食を導入する」「フェリスの公用語を英語にする」をテーマとして生徒たちが肯定派と否定派各三~四名に分かれ、それぞれレジュメとスライドを用意して議論を行いました。本授業では審査役についても生徒が務め、定められた基準に従って各チームの議論を評価する形式で勝敗を決します。
議論の中では、肯定派・否定派共に、単に議題のメリットやデメリットを思いつくままに列挙するのではなく、「そもそも学校給食の役割とはなにか」「公用語を英語にする効果とはなにか」といったテーマの芯となる問いを立て、その視点に基づきながら自らのチームの立場の論理を構築することができていたのが印象的でした。また、省庁の資料や専門書といった信頼性の高いデータを示すことで、自らの主張をより盤石に固めてゆこうとする姿勢が見えるなど、四月から本授業で学び始めた「ことば」による議論の技術が着々と身に着いている様子も伺えます。
また、互いのチームへの反駁では、予想外の質問に対しても手持ちの資料から状況を類推し、臨機応変に対応している姿もたびたび見られました。この臨機応変さの度合いは、主張の論理性・資料や論の精密性・時間管理力などと並んで、審査役の生徒たちにとっても重要な判断材料となっていたようです。
このように、「国語表現」は、参加者全員が真剣に自分の意見を発し、仲間の意見には真摯に耳を傾け、さらに自他の意見の相違や共通点について熱心に考えることが必要とされる授業です。この授業内では、すべての参加者が真っ向から「ことば」に向き合っています。
国語は、文法の学習や文章の講読、あるいは作文など、机上の学問というイメージが強い科目かもしれません。しかしながらフェリスでは国語という科目を、「自分の頭の中にあるものを『ことば』という共通手段で表現すること、また『ことば』で表現されたものを通して他者との相互理解を行うことを目指して、『ことば』の練習をする科目」と位置付けています。
仲間から発される生きた「ことば」と真摯に向き合い、互いに切磋琢磨する「国語表現」の授業は、そのような「ことば」の学問としての国語の実践の場として、フェリスの国語教育の中で重要な役割を果たしているのです。